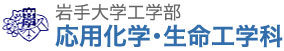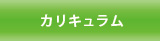先輩の声を紹介します。
 やっぱり化学っておもしろい。
やっぱり化学っておもしろい。

もともと化学が好きだということもありますが、医療関係や環境問題など自分の興味がある分野について研究しているのが応用化学科であったため進学を決めました。
大学入学後は、高校とは全く違う大学の授業に戸惑い、苦労したことが多くあり、そのたびにまわりの友人や先生方に教えていただいたことを覚えています。
大学院への進学を決めたのは、4年生になり研究室の成田教授に進学を勧められてからと遅い時期ではありましたが、大学院試の勉強をしているうちに、やっぱり化学っておもしろい、あと2年間勉強したい、という気持ちがより強くなったため、今は進学を選んで本当によかったと思っています。
2年間という時間はとても短いと思いますが、学べることはたくさんあると思うので、『授業、実験+α』を学ぶことを目標に頑張りたいです。卒業後は環境関係の職に就きたいと思っているため、そのために在学中に公害防止管理者と環境計量士の資格に挑戦したいです。
 今注目されている「エネルギー問題」に取り組んでいます。
今注目されている「エネルギー問題」に取り組んでいます。

高校時代から化学の授業が好きで、もっと専門的なことを学びたいと思い、応用化学科を選びました。大学に入学してからの勉強は、とても難しく大変でしたが、学生寮で生活していたこともあり、その寮の仲間と相談しながら取り組んでいました。
4年生になってからは、研究室に所属してリチウムイオン二次電池用正極材料についての研究を行ってきました。リチウムイオン二次電池は携帯電話やノートパソコンなどの小型電源から、電気自動車などの大型電源への応用が期待されています。 非常に注目されている分野であるため、この研究室を選び、エネルギー問題に取り組みたいと思いました。
研究室での生活は、最初は分からないことが多く失敗することばかりでしたが、毎日実験をしていくことで失敗も減り、研究をしていく面白さを知ることもできました。卒業後は、大学院に進学してさらに知識や技術を身につけて、社会に出ても通用する研究者になれるよう日々頑張っています。
 自ら考え、行動し、充実した毎日が。
自ら考え、行動し、充実した毎日が。
私は「家から近い」という理由で岩手大学を志望しました。応用化学科を選択したのは化学が得意だからです。目標を持たないまま入学したものの、応用化学科の授業や実験はとても興味深く、サークル活動では水泳部に所属し、毎日が充実していました。また、大学生活に慣れたころからアルバイトを始め、責任感を養うことができました。
4年次の研究室配属は、以前から興味を持っていた「リチウムイオン二次電池」に関する研究ができる応用電気化学研究室を希望し、そして希望通りの配属となりました。研究室では毎日実験を行い、得られたデータについて考察していきます。先生や先輩方に助けてもらうこともありますが、基本的に自ら考え、行動していく必要があります。確かに大変な毎日ですが、1~3年次とは異なった充実感があります。私は、大学を卒業後、大学院へ進学し研究者を目指し日々研究を行っていきます。
 社会に出ても活躍できるのスキルを身につけたい。
社会に出ても活躍できるのスキルを身につけたい。
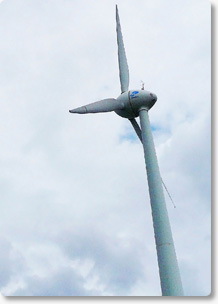
最初は家から近いという理由で岩手大学を志望していました。岩手大学のオープンキャンパスに参加し、有機半導体、リチウムイオン電池の研究に大きな関心を持ち、応用化学科を選びました。
大学に入学してからは、勉強を中心に、アルバイトやサークル活動といった社会活動に積極的に取り組みました。応用化学科の勉強は大変難しいですが、学べば学ぶほど充実感も得ることができます。
研究室に所属してからは、リチウムイオン二次電池用負極材料の研究に携わりました。現在、リチウムイオン二次電池は、携帯電話やノートパソコンなどの小型電子機器用電源に使用されています。今後は、ハイブリット自動車や電気自動車などの大型電源への応用が期待されており、リチウムイオン二次電池には様々な可能性があり、魅力的な分野であるため、この研究室を選びました。
研究室では、毎日自分で考え、自分で実験を行ないます。そのため、大変なことも多いですが、社会に出ても活躍できるためのスキルを身につけることができます。卒業後は、大学院に進学し、研究者を目指して日々研究を行っていきます。
 今までに経験したことのないことがたくさんあり、新鮮です。
今までに経験したことのないことがたくさんあり、新鮮です。
私は高校までに学んできた教科の中で、特に興味を持ったのは化学でした。化学の中でも電池に関する分野に強く関心を持っていました。大学に入学したら、電池のことや化学について深く学びたいと考えていました。進路を決めるにあたり、岩手大学には、私が現在所属している応用電気化学研究室があることを知りました。ぜひともここで勉強したいと思い進路を決定しました。
大学の勉強は奥が深く、難しく感じました。考えて答えを導くという力が必要です。テストが近くなると、友人と勉強することも多くありました。勉強の他にも大学生活はサークル活動やアルバイトなど、今までに経験したことのないことがたくさんあり、新鮮なものです。
現在は研究室に所属していて、リチウムイオン二次電池についての研究をしています。3年生までとは違い、自分なりに考え、実験を進めていきます。研究活動は苦労もありますが、充実した生活を送っています。卒業後は大学院に進学し、さらに化学や電池について学び、社会に貢献できる研究者になりたいと考えています。
 大変なことも多いけど、その分得られるものも大きい。
大変なことも多いけど、その分得られるものも大きい。
高校時代に地球温暖化による環境問題やエネルギー問題に興味を持ち、それらの研究を行なっている応用化学科を志望しました。
入学後3年間は、座学や実験を通して化学の基礎的な知識や実験の仕方を学びました。試験はどの科目も難しいので、毎日の積み重ねが重要になってきます。また、勉強の他にもアルバイト、サークル活動、ボランティアなどの課外活動も積極的に取り組みました。
4年生になると、研究室に配属されて、そこで一年間卒業研究を行ないました。
私が所属していた研究室ではリチウムイオン電池についての研究を行っており、私はその中でも正極材料について研究を行っていました。研究室では、ただ実験を行うだけでなく、実験で得られたデータに対する考察を行わねばならず、大変なことも多いですが、その分得られるものも大きいです。卒業後は大学院へ進学し、そこで学んだことを活かして社会に貢献したいと考えています。
 化学の幅広さを理解できる事ができます。
化学の幅広さを理解できる事ができます。
高校時代に岩手大学のオープンキャンパスに参加し、楽しい実験を実際に体験できた事で関心を持ち、今の学科を選びました。高校時代から化学の授業の学生実験は好きでしたし、物質を合成する過程を考える事はとても魅力的でした。
大学に入学してからは、最初に基礎的な化学を学習し、化学の幅広さを理解できる事ができました。試験は難しく、試験前に友人と分からない事を相談しながら徹夜することもありましたが、勉強の成果が出せた時はとても嬉しかったです。
4年生になってからは、電気化学の研究室に配属しリチウムイオン二次電池用正極材料についての研究を行っていました。携帯電話などの小型電池から、電気自動車などの大型電池への応用が期待されており、将来注目される分野であると考え今の研究室を選びました。実験をする度に再現性が求められますが、毎日努力して行ってきた事は社会に出ても活かすことができると思いました。卒業後は、研究者ではありませんが大学で学んだ日々の努力を発揮できると信じています。
 教科書で勉強するだけではわからない事も学びます。
教科書で勉強するだけではわからない事も学びます。

私が応用化学科を志望したのは高校三年生のときのオープンキャンパスがきっかけでした。高校では化学と物理を選択していたため、その時は工学部を中心に見学に行きました。そこで応用化学科のとある研究室の見学へ行ったところ、その研究室では廃棄貝殻など未利用資源を活用した研究をしていました。
私自身環境問題について学びたかったというのもあって、とても興味を持ちました。また、工学部は男性が多いというイメージがあったのですが、応用化学科は工学部のその他の学科と比べると女性が多かったので、大学生活が過ごしやすくなると思い、それも応用化学科を志望した理由の一つです。
学部での生活は、二年生までの授業が午前中で終わることが多かったので、サークル活動やアルバイトと充実した毎日を過ごしました。三年生になると化学の学生実験が始まるので、教科書で勉強するだけではわからない事も実験を通して学ぶことができました。
四年生になると研究室に所属し、卒業研究に励む毎日です。また研究室ではお花見などのイベントもあり、研究の合間のいい気分転換もできました。卒業後は岩手大学大学院に進学し、四年生で学んだ分野をより深く学ぶつもりです。
 様々なことを身につけ、充実した大学生活を。
様々なことを身につけ、充実した大学生活を。

私がこの応用化学科を選んだ理由は、高校では化学が得意科目だったことから、大学でも化学を継続して勉強し、社会に出てからも化学の知識を生かしていきたいと考えたからです。
私の学部での生活については、部活動やアルバイトをやっていたのでそれらと学業の両立に苦労しましたが、様々なことを身につけられたと思います。
研究室に入ってからは実験を行ったり、自分の研究分野に関する文献を読んだりして過ごしていました。また、研究室ではいも煮会や忘年会などのイベントも多々あり、非常に楽しかったです。今振り返ると、充実した大学生活を送れたと思いますが、勉強や実験などをもっと計画的に行うことができたのではないかと反省しています。
卒業後は大学院に進学し、現在研究を行っているトライボロジー(摩擦・摩耗に関する科学)を引き続き研究していきます。卒業研究の1年間では勉強しきれなかったことを身につけ、解明されていない現象について深く追求していきたいと思っています。
 自分から学びたいという意思が大切。
自分から学びたいという意思が大切。
私は高校生のとき、人の役に立つ職業に就きたいと考えていました。しかし、人の役に立つ職業と言っても様々あり、なかなか決めることができずにいました。そのときに、担任の先生から直接人と接する職業ではなくて物を作ったり、工学的な面からでも人の役に立つことができるんだよ、と言われて福祉システム工学科に入りたいと思いました。
大学に入学してからは、高校生活と違うところがたくさんあり最初は戸惑いました。大学は誰かから言ってもらうのを待つのではなく、自分から学びたいという意思がないといけないと実感しました。大切な友達もたくさんできてとても楽しく大学生活を送ることができました。アルバイトも4年間続けることができ、働 くことの大変さも知ることができ、とてもいい経験をすることができてよかったです。
卒業後はものづくりの仕事なので自分にできるのか不安はありますが、一生懸命がんばっていきたいと思います。
 多角的な方面から結果に対し検討・考察する力を養おう。
多角的な方面から結果に対し検討・考察する力を養おう。
「福祉」という分野に興味を持っており、生体の構造や機能を解明して、その作動原理を工学的観点から理解していくこの福祉工学という学科に非常に興味がありました。
神経系や運動系について学ぶ生体情報処理や、医療・福祉機器の基礎を学ぶメディカルエレクトロニクスなど様々な分野の授業があり、大学時代を通して人々の生活を支える医療機器に対する認識が大きく変わったことがとても印象的です。
その中で、生体に対する生理学的変化の研究に興味を持ち、研究室は脳波・赤外線を測定・解析する研究室に所属し、生体への電気生理学的効果について研究をしました。
生体はその時のコンディションだけじゃなく感情状態も大きな影響を及ぼすので、多角的な方面から結果に対し検討・考察する力を養うことができたと思います。
卒業後の進路は通信系の会社ですが、自分の興味のあった分野を学べた4年間だったので、とても充実した大学生活でした。