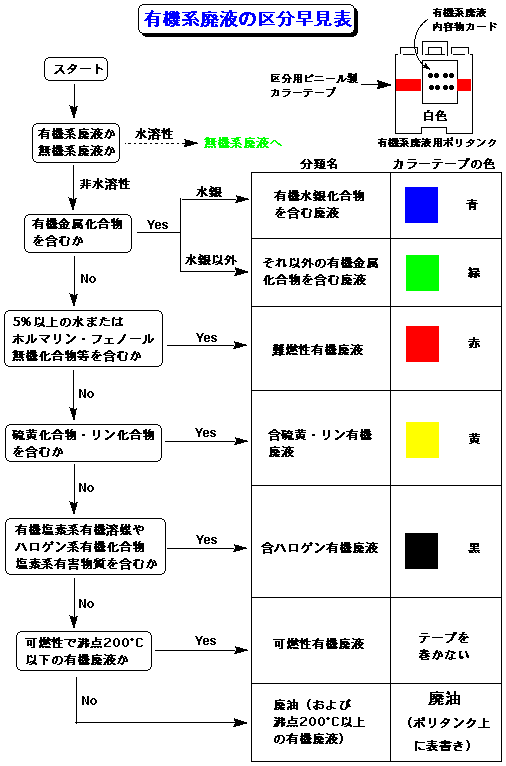
有機系廃液
3-1 有機系廃液の区分
有機系廃液の取扱については、燃えやすい溶剤が多いので貯留に関して消防法上の注意が必要である。また環境汚染に対する配慮の面では廃棄物処理法に関わる注意事項に留意する必要がある。岩手大学では有機系廃液を可燃性廃液、難燃性廃液、有機水銀化合物を含む廃液、それ以外の有機金属化合物を含む廃液、含イオウ・リン有機廃液、ハロゲン系化合物を含む有機廃液、および廃油、の7種類に分類する。さらに有機系廃液の貯留には白色のポリタンクを指定するので、廃液を出す者は下記の有機系廃液区分早見表(図4)に応じてそのポリタンクの胴体部分に指定された色のビニール製のカラーテープを巻き、それぞれの廃液を混合することなく厳密に貯留・保管する。有機系廃液の回収の際にはそれぞれの容器に内容物表示カード(図5)を貼り付けて提出する。
なお、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」ではベンゼン・ジクロロメタン・四塩化炭素が特別管理産業廃棄物として指定されており、有害物質としての取扱が求められている。また「PRTR法」ではいわゆる有機溶媒としてはベンゼン・トルエン・クロロホルム・ジクロロメタン・アセトニトリルなどについて購入・保管・移転等の厳正な管理と移転記録の保持が求められている。これらの点に十分に留意しながら、有機系廃液の排出・貯留を行って欲しい。また有機系廃液は消防法の適用対象でもあるから、大量の有機系廃液を研究室・実験室等に貯留・保管してはならない。その保管には施錠のできる廃液保管庫等(換気装置と消火装置付き)を部局あるいは学科等の単位で用意することが望ましい。
有機系廃液の分類は以下の通りである。
1. 有機水銀化合物を含む廃液
酸化処理をしない有機水銀化合物をそのまま含む廃液。有機水銀化合物は過マンガン酸カリウム等により酸化分解した後、水銀系無機廃液として貯留・保管するべきである。ただし酸化処理が困難な場合には「有機廃液:有機水銀化合物を含む廃液」のままで実験廃液として出してよい。
2. それ以外の有機金属化合物を含む廃液
有機金属含有廃液、特に重金属化合物を含有しているもの。
3. 難燃性廃液
ホルマリン、有機酸(酢酸・トリクロロ酢酸・メタンスルホン酸等)、アミン類(メチルアミン・エチルアミン等)、水と有機溶媒の混合廃液、難分解性シアン錯体、フェノール類などの水溶性有機化合物の廃液など。
4. 含イオウ・リン有機廃液
低沸点のチオフェンなどのイオウ化合物や有機リン化合物を含んでいて、それ自身が著しい悪臭や毒性を有するもの。あるいは燃焼等により有毒ガス等が発生する可能性のあるもの。
5. ハロゲン系有機廃液
脂肪族・芳香族ハロゲン系化合物の廃液。 クロロホルム・ジクロロメタン・四塩化炭素等はいずれも「ハロゲン系有機廃液」に含めてよいが、廃液中にそれらが含まれている場合は当該有機化合物をどの程度含んだ混合廃液であるかの表示が必要となる。
6. 可燃性廃液
脂肪族炭化水素、同酸素化合物、同含窒素化合物、芳香族化合物、同含窒素化合物などの廃液。 ベンゼン・トルエン・アセトニトリルはいずれも「可燃性廃液」に含めてよいが、廃液中にそれらが含まれる場合はそれぞれをどの程度含んだ廃液であるかを表示することが必要である。従ってこれらの成分を含有する有機系廃液は通常の可燃性廃液と区別回収することが好ましい。
7. 廃油
灯油、軽油、重油、機械油、動植物油など、 高沸点の可燃性廃液。
3-2 有機廃液貯留上の注意点
有機系廃液貯留の際の一般的注意として、以下の6点を守って欲しい。
(1) 有機系廃液区分早見表(図4)を廃液用ポリタンク等の設置場所の目立つ所に掲示し、それぞれの区分に属する有機系廃液を混合することなく厳密に貯留・保管する。
(2) 有機系廃液の保管には施錠のできる廃液保管庫等(換気装置と消火装置付き)を用いる。
(3) 有機系廃液の回収には指定された白色のポリタンクを使用する。
(4) ハロゲン系有機廃液とその他の廃液とは混合しないこと。塩素系の溶媒(ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,2-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン)およびベンゼンは有害物質として規定されており、これらは特別管理産業廃棄物として取り扱われなければならない。また上記以外の塩素系溶剤についても燃焼処理をする際に有害な塩酸ガス等を発生するため、特別管理産業廃棄物として分別回収貯留することが求められる。
(5) 重金属の混在する有機系廃液はできるだけ各研究室ごとに適正な前処理を行い、可能な限りは無機系廃液として出すこと。金属錯体等については金属を水相に抽出するか、溶媒を蒸留して分離すること。重金属が混在する有機系廃液は処理業者が燃焼処分を行うため燃えた後の灰分は特別管理産業廃棄物として処理される。
(6) 水の含有量が5%以上の有機系廃液は難燃性有機系廃液として取扱う。
有機系廃液を出す研究室は必要な廃液回収用ポリタンクの必要数を環境保全委員会に申し出て必要個数を受け取り、その容器に有機系廃液のみを区分貯留する。岩手大学では有機系廃液を定期的(1年あたり2度)に回収し一括して廃液処理業者に引き渡し、処理業者はそれぞれの廃液を容器ごと焼却処分する。各研究室では廃液回収用ポリタンクにほぼ90%ほど廃液の入った状態を廃液回収に出す目安として欲しい。出る廃液量がごく少量と見込まれる区分のものについてはポリタンクではなく分類用カラーテープを巻いた500ミリリットル程度のポリエチレン瓶等(ふたで密閉できる容器。ただしガラス瓶は不可。)などに区分保管する。廃液回収の際にはそれぞれの廃液回収用容器に内容物表示カード(図5)を貼り付けて提出することになる。内容物表示カードの「含有物の種類・量等」欄にはその廃液回収容器に関する回収履歴の集計結果を正確に記載する。
図4 有機系廃液区分早見表
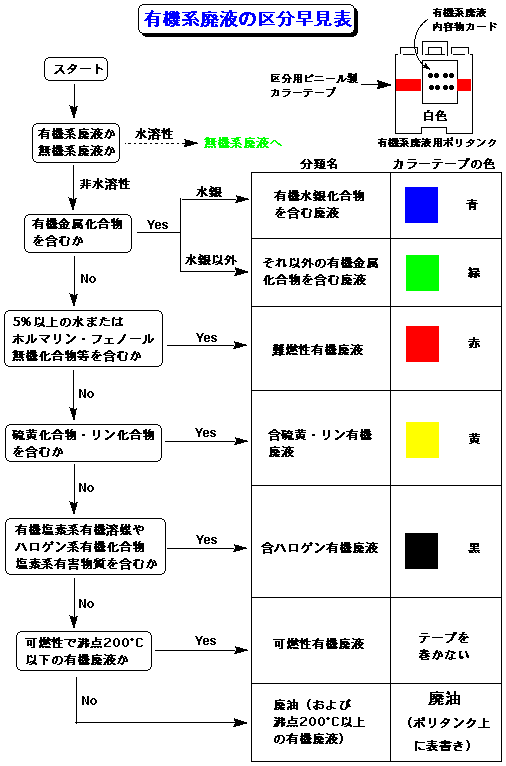
図5 有機系廃液内容物カード
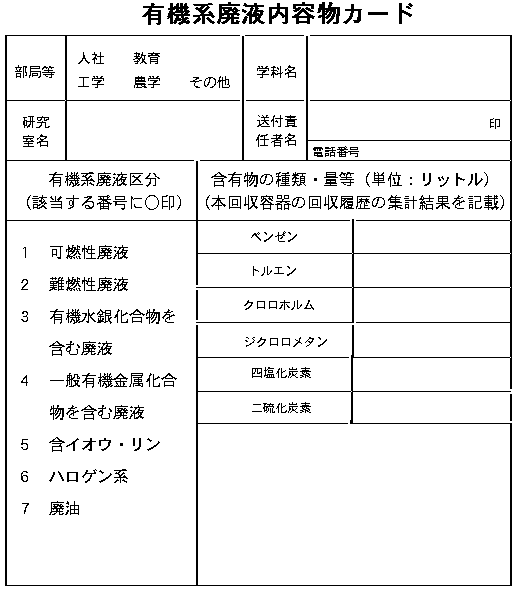
<岩手大学環境保全委員会発行の「岩手大学 実験廃液マニュアル 第1版」について>
「岩手大学 実験廃液マニュアル 第1版」は岩手大学環境保全委員会が平成15年12月に作成し平成16年3月に岩手大学の化学系教職員に無料で配布した冊子であり、その中では教育研究活動を安全に進めていくために書かせない有機無機廃液の分別と回収に関する注意事項が細かく記載されている。本冊子の内容に関する問い合わせや取り寄せの希望等は下記の部署で取り扱っている。
〒020-8551 岩手県盛岡市上田3丁目18-8 岩手大学財務部施設課機械係(TEL 019-621-6046, e-mail: kikai@iwate-u.ac.jp)