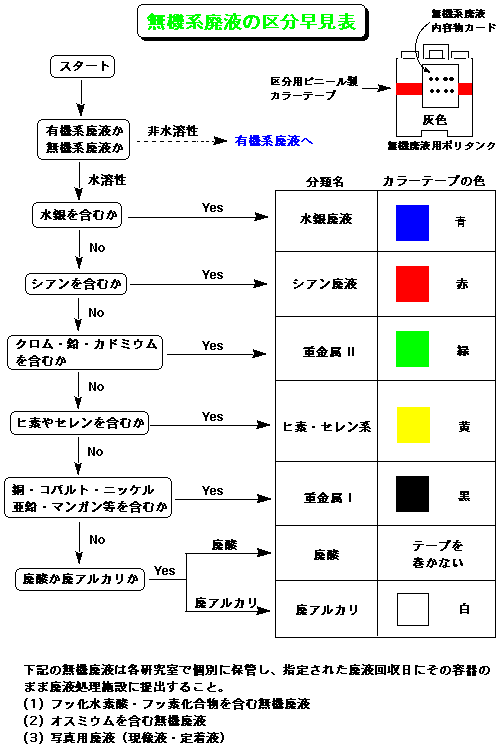
無機系廃液
2-1 無機系廃液の区分
無機系廃液には、水銀系廃液、シアン系廃液、クロム・鉛・カドミウム等の重金属廃液、ヒ素・セレン系廃液、銅・コバルト・ニッケル・亜鉛・マンガン等の重金属廃液、酸廃液、アルカリ廃液、フッ素系廃液、写真現像廃液、写真定着廃液、が含まれる。岩手大学ではフッ素系廃液、写真現像廃液、写真定着廃液を除く無機廃液の貯留には灰色のポリタンクを指定するので、無機系廃液を出す者は無機廃液区分早見表(図2)に応じてそのポリタンクの胴体部分に指定された色のビニール製のカラーテープを巻き、厳密に分別・保管する。無機系廃液の回収の際にはそれぞれの容器に内容物表示カード(図3)を貼り付けて提出する。
無機系廃液の分類は以下の通りである。
1. 水銀含有廃液
水銀化合物を含む廃液は特に厳密に「水銀含有廃液」として貯留する。なお、金属水銀はここには該当しない。有機水銀は酸化分解により無機水銀に変わるので、有機水銀化合物や有機物が含まれる場合には過マンガン酸カリウム等により酸化分解した後貯留すること。なお酸化分解の際に酸化分解処理過程で水銀の蒸気が発生することがあるので、十分気を付けること。なおシアン化物イオンの混入した水銀含有廃液に対してはアルカリ条件下で10%次亜塩素酸ナトリウム水溶液を加えて数時間放置し、次いで亜硫酸ナトリウムを加えて残留塩素を還元し、シアン化物イオンの存在しないことを確認してから通常の水銀含有廃液と同様に取り扱う。
<付> 水銀化合物の取扱操作がわからない場合などは熟練者または各部局の環境保全委員に相談すること。また有機水銀の酸化処理が困難な場合には「有機廃液:有機水銀化合物を含む廃液」として実験廃液を出す。
2. シアン含有廃液
シアン化水素、シアン化物、重金属のシアン錯塩、フェリシアン・フェロシアン・チオシアン酸などを含む廃液。シアン化物イオンは酸性側ではシアン化水素(HCN)の気体(猛毒)となって大気中に拡散するから、必ずアルカリ性(pH12程度)で貯留。なお錯シアン化合物(金属とシアン化合物の錯体)はフェライト法では処理困難なので、可能な限りシアン廃液中には重金属類を混入させないこと。
<付> シアン化物を含む廃液の取扱操作がわからない場合は熟練者または各部局の環境保全委員に相談すること。
3. 重金属 II 廃液
クロム酸混液などのクロム系化合物廃液、鉛・カドミウム等の高毒性重金属を含む廃液。 これらの重金属塩はいずれも毒性が高く「特別管理産業廃棄物 」に該当するので、廃液を出す研究室等は可能な限りこれらの重金属イオンの混合を避け、内容物を明確に表示して貯留・保管する。なお重金属 II 廃液の貯留は必ず酸性の状態で行うこと。
4. ヒ素・セレン系廃液
ヒ素・セレン系化合物を含む廃液。 これらの化合物はいずれも毒性が高く「特別管理産業廃棄物 」に該当しているので、可能な限り「ヒ素系廃液」と「セレン系廃液」を区別して貯留・保管する。さらにセレン系廃液は硝酸酸性にしておき、容器内への金属セレン粉末などの混入を避ける。
5. 重金属 I 廃液
銅・コバルト・ニッケル・亜鉛・マンガン等の比較的毒性の低い重金属を含む廃液。重金属 I 廃液は酸性で貯留すること。
6. 廃酸
重金属を含有しない酸性廃液。硫酸、塩酸、硝酸、過塩素酸等がここに該当する。ただし、pH5〜9の水溶液は上記の1〜5項に該当する物質やフッ素、オスミウム等を含まない限りにおいては無機廃液として回収する必要はない。
7. 廃アルカリ
重金属を含有しないアルカリ性廃液。アンモニア水・ヒドラジン・苛性ソーダ、苛性カリ等がここに該当する。ただし、pH5〜9の水溶液は上記の1〜5項に該当する物質やフッ素、オスミウム等を含まない限りにおいては無機廃液として回収する必要はない。
なお、フッ素系廃液、写真現像廃液、写真定着廃液、特別管理産業廃棄物として特に指定されているオスミウム類を含む廃液は研究室単位でそれぞれ特定の貯留容器を用意し、その中に当該廃液を回収貯留する。
1. フッ素含有廃液
フッ化水素酸、フッ化物塩等を含む廃液。濃厚なフッ化水素酸を廃液とする場合は貯留・搬入・移液・処理の各段階で危険を伴う恐れがあるため、少量ずつ希釈・中和して(操作には十分注意)pH1〜2程度以上で貯留すること。フッ素廃液は無機廃液のフェライト処理を妨害する。フッ化物イオンは多くの金属と安定な錯体を形成しやすいので無機廃液中の各種金属イオンの処理・除去にフッ化物イオンの共存は好ましくない。従ってフッ化物イオンを含む廃液と他の廃液とを混合しないように重金属とは別に収集する。
2. オスミウム含有廃液
オスミウミ化合物を含む廃液。毒性が極めて高いので、他の重金属廃液と混合しないように分別収集する。
3. 写真廃液
写真廃液は現像廃液と定着廃液に区分して貯留・回収する。
2-2 無機廃液貯留上の注意
無機系廃液貯留の際の一般的注意として、以下の5点を守ること。
(1) 無機系廃液区分早見表(図2)を廃液用ポリタンク等の設置場所の目立つ所に掲示し、それぞれの区分に属する無機系廃液を混合することなく厳密に貯留・保管する。
(2) 無機系廃液の保管には施錠のできる廃液保管庫等(換気装置と消火装置付き)を用いる。
(3) 無機系廃液の回収には指定された灰色のポリタンクを使用する。
(4) 無機系廃液には有機物を含まないこと
有機化合物の混入はCOD,BOD値を高め、廃液の処理を妨害すると共に、処理装置に重大な障害を与える恐れがある。従って貯留の段階で有機化合物が混入しないよう十分に注意すること。
(5) 固形物を混入しないこと
固形物(ガラス片,ろ紙,その他)を廃液中に入れてはならない。
(6) 無機系廃液の一次洗浄水はあくまでも無機廃液として取り扱い、けっして流し等に放流してはならない。
(7) 放射性物質を含まないこと
(8) ウイルス,細菌に汚染されたものを含まないこと。
無機系廃液を出す研究室は必要な廃液用ポリタンクの必要数を環境保全委員会に申し出て必要個数を受け取り、その容器に無機系廃液を区分貯留する。岩手大学では無機系廃液を定期的(1年あたり2度)に回収し、一括して廃液処理業者に処理を委託する。各研究室では1個の廃液用ポリタンクにほぼ90%ほど入った状態をその廃液を回収処理に出す目安とする。出てくる廃液量がごく少量と見込まれる区分のものについてはポリタンクではなく分類用カラーテープを巻いた500ml程度のポリエチレン瓶等(ガラス瓶は不可)などに区分保管する。廃液回収の際にはそれぞれの廃液回収用容器に内容物表示カード(図3)を貼り付けて提出することになる。内容物表示カードの「含有物の種類・量等」欄にはその廃液回収容器に関する回収履歴の集計結果を正確に記載すること。
図2 無機系廃液区分早見表
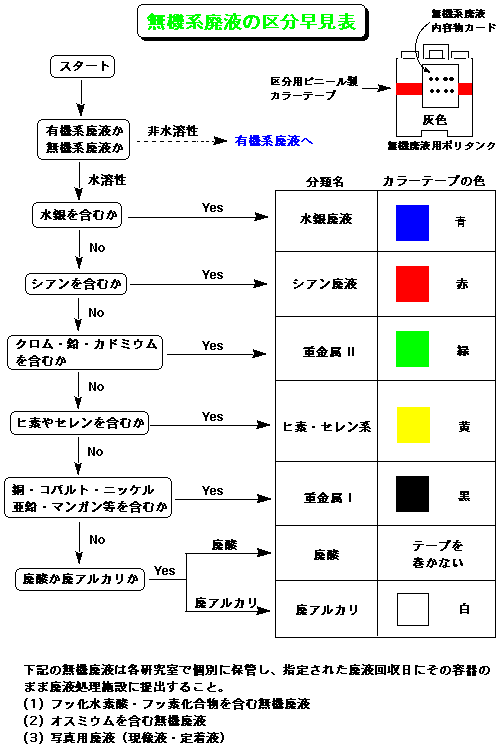
図3 無機系廃液内容物カード
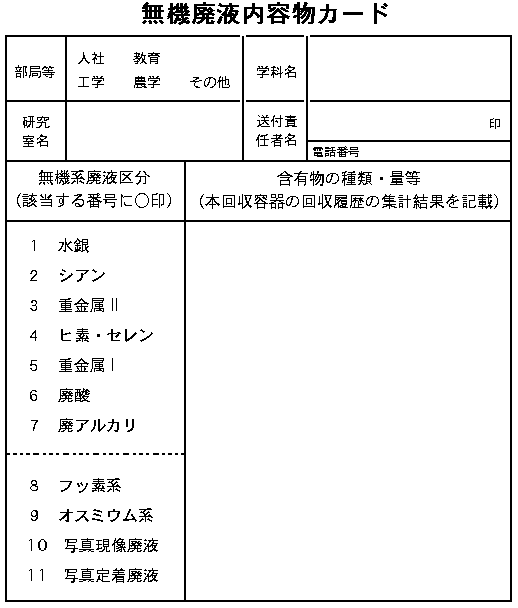
<岩手大学環境保全委員会発行の「岩手大学 実験廃液マニュアル 第1版」について>
「岩手大学 実験廃液マニュアル 第1版」は岩手大学環境保全委員会が平成15年12月に作成し平成16年3月に岩手大学の化学系教職員に無料で配布した冊子であり、その中では教育研究活動を安全に進めていくために書かせない有機無機廃液の分別と回収に関する注意事項が細かく記載されている。本冊子の内容に関する問い合わせや取り寄せの希望等は下記の部署で取り扱っている。
〒020-8551 岩手県盛岡市上田3丁目18-8 岩手大学財務部施設課機械係(TEL 019-621-6046, e-mail: kikai@iwate-u.ac.jp)